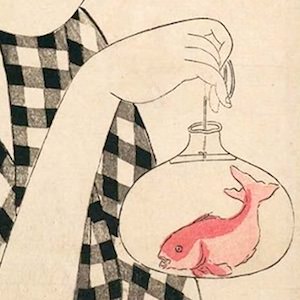江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!
チャンネル登録をお願いします!
その5 風鈴(ふうりん)
現代のようなガラスの風鈴が登場したのは江戸時代のことで、チリンチリンという涼しげな音色で耳から涼を感じました。ガラス風鈴が江戸に登場した当初、長崎のガラス職人がわざわざやってきてつくったそうで、ガラスが貴重品だったこともあり、お値段はなんと現代の金額で200万円以上もしたとか。
スポンサーリンク
その後、江戸でもガラス細工が盛んになるとガラスの風鈴も手ごろな値段となり、夏には天秤棒に風鈴をぶら下げた風鈴売りが売り歩きました。素材としてはガラスのほか、金属製のものや陶器製のものもありました。

江戸時代の風鈴。形状も現代のものと同じ(松斎長喜 画)
その6 釣りしのぶ
ちょっと聞きなれないこちらも、江戸時代に江戸で生まれた夏のインテリア。釣りしのぶは、竹の棒などにコケを巻きつけ、その上にシダの一種である「しのぶ」をはわせ、屋形船や灯籠、筏などさまざまな形に仕立てたもので、軒下に吊るして楽しみました。
江戸時代の庭師が手慰みに始め、出入りの屋敷にプレゼントしたのが始まりといわれ、江戸時代末期には庶民にも広まったそう。
夏の季語でもあり、江戸時代を代表する歌人・小林一茶も「水かけて 夜にしたりけり 釣荵(つりしのぶ)」と詠んでいます。

鮮やかな緑は見た目にも涼しげ。現在、釣りしのぶ工房は都内では1軒だけ。画像引用元:江戸美学研究会