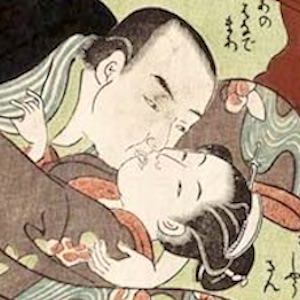世界最古の入れ歯はなんと日本製
歯のケアに気をつけてはいても虫歯にはなるもの。そして、最終的に入れ歯のお世話にならなければ……なんてことも。
日本での入れ歯の歴史は意外や意外とっても古く、なんと弥生時代の遺跡から石製の義歯が発見されています。
現存する世界最古の入れ歯もなんと日本製!
スポンサーリンク
戦国時代の1538年(天文7)に74歳で亡くなった紀伊国(現・和歌山県)の願成寺(がんじょうじ)の尼僧・仏姫の入れ歯で、すべて木でできた入れ歯、「木床義歯(もくしょうぎし)」と呼ばれるものです。安土・桃山時代には仏師が副業で入れ歯を作っていたとか。

江戸時代のものと考えられている入れ歯。
歯茎は木製で、歯は蝋石でできています。ちなみに入れ歯を作るのは医師ではなく職人で「口中入歯師」と呼ばれていました。
今ではスーパーやドラックストアにずらりとデンタルケア商品が並んでいますが、江戸時代にもすでにさまざまなデンタルケアグッズがあったなんて驚きです。
歯磨き習慣といい、今に続く習慣がほんとにたくさん江戸時代にルーツがあるんですね。